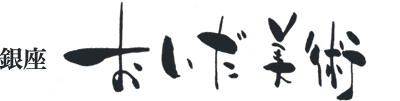日本とゴッホ
— 2023年11月2日先日、ある集まりでアート・キュレーション代表の美術評論家村上哲さんの「アートは国境を超えて」と題する講演をお聴きしました。村上さんは比較芸術学が専門で、日本の浮世絵とフランス絵画の出会いについてのとても興味深いお話だったのですが、その中で、ゴッホの作品の紹介もあり、「へえ こんなに深い影響があるんだ」と感心しました。
ゴッホはオランダで1853年(日本では江戸時代の末期で、あと15年で明治維新です)生まれですが、1888年(明治21年)の35歳の時の自画像は、「自らを日本の坊主(僧侶)として描いたアルル時代の自画像」なんだそうです。
私は、この自画像を以前から見たことはあったのですが、「自らを日本の坊主(僧侶)として描いた」とは知りませんでした。ゴッホが浮世絵の影響を受けていたことも多少聞いたことはあるのですが、村上さんのお話では、「日本の芸術や文化のみならず、精神的な在り方そのものに憧れていたゴッホは、日本の精神文化の象徴としての「僧侶」の姿に自分を託して描いた」そうです。
ゴッホは牧師の家で生まれて、聖職者を志していたそうですから、そのせいかもしれませんが、「日本の精神文化」って何でしょう。「日本の精神文化の象徴」は、「神主(神道、天皇)」や「武士(武士道)」じゃなくて、ゴッホには「僧侶」だったんですね。「僧侶」って、出家して世俗の生活を捨てて、仏教の戒律を守り修行をしている人のことですが、この時のゴッホは、日本の「僧侶」の姿に自分を託したんですね。
またゴッホは、日本の「花魁」にも魅了されていたようです。「花魁」は吉原遊廓の遊女で位の高い女性のことをいうんですが、とても綺麗な作品です。
当時のパリは、万国博覧会の影響で、日本趣味(ジャポニズム)が、非常に流行していたそうです。ヨーロッパの人には、江戸時代の日本がどう映ったんでしょう。すごく異質な、でも魅力的な文化と映ったんじゃないでしょうか。
ゴッホは浮世絵のカラフルな色使いや、大胆な筆遣い、明確な輪郭線などに、新たな可能性を見出していきました。そして、浮世絵の模写からスタートし、徐々にそのエッセンスを作品に取り入れていったそうです。「花魁」は、日本画家渓斎英泉の浮世絵を模写したものです。
そしてゴッホは、当時安価で入手できた浮世絵の熱心な収集家でもあったそうです。オランダのアムステルダムにあるゴッホ美術館には、なんと、ゴッホと弟のテオが所有していた477点もの浮世絵が収蔵されているそうで、私が思っていた以上に日本文化に造詣が深かったようです。日本における「僧侶」の精神性や、艶やかな「花魁」(一見、相反するもののようなのですが)に、深く感銘を受けて、自分の芸術をどんどんと広げていったのでしょうね。
一言では言えないとしても、外国の人には「日本」は案外魅力的なのかもしれません。ゴッホの時代だけでなく、今だって日本の漫画(アニメ)文化は、国際的に評価されていますからね(実はこの間、宮崎駿のアニメ「君たちはどう生きるか」も見てきたんですが、よくわからなかったものの、面白かったです)。
日本人としては、何となく誇らしいような。こういう分野で、日本の存在感が高まるといいですよねえ。だって、ウクライナやらパレスチナでは、それぞれの民族の文化的宗教的な長い歴史の中で、「文明の衝突」が起こり、複雑な国際政治の力関係のなかで、今戦争になっているんですから。「日本」がアジアの周辺の国々とそんなことにはなりませんように。
なんてことを思っていたら、たまたまSONPO美術館で、「ゴッホと静物画 伝統から革新へ」の展覧会が開催されていました。「<ひまわり>、<アイリス>をはじめ25点のゴッホ作品が集結」というだけあって、こんなに沢山のゴッホをまとめて見たのは久しぶりです。
ゴッホは、絵画を扱う美術商に勤めたもののクビになったり、キリスト教の伝道師になろうとしたら「度を超えた病人や怪我人への献身ぶりが問題となり、臨時説教師の仮免許を剥奪」されてしまったそうです。それでもひたすら坑夫や酒場などをスケッチしながら、独学で絵画の腕を磨き、27歳にして、プロの画家になる事を決意します。1880年(明治13年)夏の事でした。子供の頃から絵は得意だったようですけど、1890年(明治23年)に37歳で亡くなっているんですから、画家としての活動はほんの10年間しかないんです。生前に売れた絵は1点だけだそうです。
天賦の才能って本当にあるんですね。ビックリ。
ゴッホは、最初のうちは、暗い色彩の作品ばかり描いていたようです。これはハーグ派と呼ばれる画家たちの地味で暗い色彩の作品に、強い影響を受けていたためだそうですが、1885年(明治18年)に描いた「ジャガイモを食べる人々」は、ゴッホ最初期の代表作品となっています。
1885年11月、32歳のゴッホは、ベルギーで、美術学校に通いますが、翌年に最初の学期で落第すると(ゴッホを落第させる美術学校って何なんでしょう?)、弟テオが暮らすパリの「モンマルトル」へと旅立ちます。
パリでゴッホは、ロートレックやベルナールなどとも知り合い、スーラ、ゴーギャンらとも交流を持ちながら、ひたすら芸術活動に打ち込んでいきます。
パリでの活動当初は、暗鬱な色調だったゴッホの自画像も、印象派の画家や、当時の風潮に感化され、徐々に明るく、軽やかな色使いになっていきます。
1887年(明治20年)夏頃の作品「麦わら帽子の自画像」は、パリでのゴッホの色調変化を知る上で、非常に分かりやすい一作だと言われています。
本当に素晴らしい自画像だと思いますが、当時は全く売れなかったそうですよ。
そしてゴッホは、パリで精神的に疲弊し、1888年2月、35歳の時に、南フランスの田舎町アルルへ向かいます。アルルは美しい所で、ゴッホは、アルルに、浮世絵で見た日本の美しく色調豊かな景観を重ねていたそうです。
ゴッホは、外観が黄色に塗装された建物を気に入り、そこで数部屋を借りて生活をスタートします。後にこの建物は「黄色い家」と呼ばれ、その外観を描いたゴッホの絵画は、現在も彼の代表作品になっています。
この時代のゴッホの作風は、パリ時代にも増して、色合いは鮮烈でカラフルに、筆遣いは大胆で力強くなっていきます。一般的には、このアルル時代に、炎の画家ゴッホの才能が開花したと言われています。
ゴッホがアルルに来た目的の一つに、無名画家同士で、コロニー(生活共同体)を形成したいと言う考えがありました。ゴッホが思い描くコロニーとは、画商の弟テオの援助の下で、画家たちが黄色い家でひたすら作品を描き、それらをテオに販売してもらう。そして、稼いだお金は平等に分け、そこから画材費や生活費を賄っていくと言う内容でした。
ゴッホは手始めに、パリで親交のあったゴーギャンやベルナールなどを呼び寄せようと、自身の熱い思いと構想を綴った手紙を送ります。
ゴッホの計画に興味を示す画家は皆無でしたが、アルルまでの旅費と生活費をテオが支援すると言う事で、ゴーギャンだけがコロニーへ加わる意思を示します。
期待に胸を膨らませるゴッホは、ゴーギャンが来るまでの数ヶ月間で、寝室の壁を絵画で埋め尽くそうと、4点の「ひまわり」を描きます。
ゴーギャンは、1888年10月23日、アルルに到着するのですが、12月23日、ゴーギャンと口論の末、自ら左耳を傷つける「かみそり事件」が起こります。
展覧会のカタログには、「1888年12月、制作で意見が対立し激怒したゴーギャンはパリへ帰ることをゴッホに告げます。自分の呼びかけに唯一応じてアルルへ来たゴーギャンがパリに帰る・・動揺したゴッホはカミソリを手にゴーギャンを襲うものの未遂に終わります。自省したゴッホは自己嫌悪におちいり、自らの耳をカミソリで切りました。事件後ゴッホはまず、アルルの、その後アルルに近いサン=レミという町の精神病院に入院しました。」と書かれています。
1889年から1890年までここで生活をしているのですが、その後、オーヴェール=シュル=オワーズへ向い、麦畑から銃弾を受けた状態で下宿に戻ります(自ら撃ったとされています)。そして、弟のテオに看取られ37年の生涯を閉じます。
このアイリスは、1890年5月に描かれたそうです。
アルルの明るい光や、ゴーギャンとの「かみそり事件」、精神病院への入院など様々な要因があってのことでしょうが、坊主の「自画像」も、「ひまわり」も「アイリス」も一目見れば、作品全てがゴッホそのものであり、そこにゴッホが居ることを強く訴えかけてきます。そして、その生き方や抱えていた孤独までもがひしひしと伝わってくるかのようです。
そしてそこには、西洋絵画の伝統のみならず、ゴッホに革新的な影響を与えた「日本」の文化も確かに存在しているんですね。
生前は画家として評価されなかったようですが、37年という短い人生の中で、苦悩しながらも画家としての歩みを止めなかったゴッホの芸術は、今なお後世の芸術家や現代の私たちに大きな影響を与え続けています。
私は、ゴッホの作品を見ると、それまでの他の画家の絵でも見たことのない独特な配色や鮮やかな色調には驚かされます。
これはやはりさんさんと太陽が降り注ぐアルルの気候とか日本の浮世絵の鮮やかで陰影のない平坦な絵から影響を受けたからでしょうか。精神の深いところの琴線に作品が触れてくるような気がします。
絵に生命の躍動感が吹き込まれ、人々を魅了してやまないゴッホの芸術の真髄がここにあるのでしょうね。
美術ヨモヤマ話
 藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日
藤田嗣治 「猫のいる風景」展と 挿画本「四十雀」「藤田嗣治とジャン・コクトー」展2025年3月24日 善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日
善光寺参りと東山魁夷2024年11月18日 白髪一雄と塩田千春2024年10月4日
白髪一雄と塩田千春2024年10月4日 愛知県碧南市 藤井達吉現代美術館ってご存知ですか2024年5月2日
愛知県碧南市 藤井達吉現代美術館ってご存知ですか2024年5月2日 奈良美智の少女を泣かせたのは誰?2024年2月26日
奈良美智の少女を泣かせたのは誰?2024年2月26日 エコール・ド・パリと100年後の今2024年1月31日
エコール・ド・パリと100年後の今2024年1月31日 世界のムナカタってどうやってメイキングされたの?2023年11月27日
世界のムナカタってどうやってメイキングされたの?2023年11月27日
画廊紹介

営業時間
月曜日~土曜日(日曜・祝日はお休み)
午前10~午後7時まで
詳しくはこちら
詳しくはこちら
お問合せ
電話番号:03-3562-1740
E-mail:info@oida-art.com
お問合わせフォーム
お問合わせフォーム
LINEでお問合せ
アクセス
画廊店主のひとり言
- 付け馬のついていた画商さん — 2023.12.8
- 一丁あがり、モダンタイムス時代の結婚式 — 2023.8.30
先日、ある地方に住んでいらっしゃるお方(Aさん)より電話がありました。 「B画伯とG画伯の絵を売りたいのですが。」 「保証書と共箱が付いていて、たぶん間違いの...
先日友人の娘さんの結婚式に招待され、参列してきました。 このお二人そもそもはお見合いでお付き合いが始まった話なのですが、お付き合いをするようになりましたら、...
「画廊店主のひとり言」その他のコラムはこちら
作品検索
-

棟方志功(リトグラフ)
大弁財天妃神尊像之図詳細 
藤田嗣治
鳩と少女詳細
東郷青児
想い出詳細
熊谷守一
薔薇詳細
岡鹿之助
三色スミレとななかまど詳細
三岸節子
花 ヴェロンにて詳細
谷内六郎
四季版画より“春”詳細
山下清
ダリア詳細
西村計雄
あねもね詳細
笠井誠一
チューリップ詳細
絹谷幸二
朝陽黄金雲上不二詳細
斎藤清
春の鎌倉 円覚寺詳細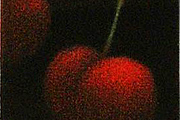
浜口陽三
One and One-Half詳細
山本容子
かごめかごめ詳細
マティス
“ヴェルヴ”より Decor...詳細
デュフィ
春の花 1 (ムルロリト...詳細
ユトリロ
霊感の村より「ムーラ...詳細
パブロ・ピカソ
スケッチブックより ...詳細
ミロ
鏡の女詳細
ベルナール・ビュッフェ
赤と黄色のチューリップ詳細
カトラン
マリーゴールドとアネ...詳細
ジャンセン
あざみのある静物詳細
アイズピリ
黄色いバックの花束詳細
アンドレ・ブラジリエ
バラ色の空詳細
カシニョール
アニバーサリー(小)詳細
アンディ・ウォーホル
FLOWERS 2詳細
キース・ヘリング
Tree of Life詳細
バンクシー
GIRL WITH RED BALLOON...詳細
草間彌生(草間弥生)
絵皿(YELLOW FLOWER)詳細
村上隆
両手を大きく広げて幸...詳細
奈良美智
Miss Spring詳細
ロッカクアヤコ
魔法の手 展覧会ポスター詳細
小松美羽
守護獣 土詳細
KYNE(キネ)
Untitled(Longing for...詳細
ドラクロワ
恋人達の四季 春詳細
ヒロヤマガタ
ゴルファーズ詳細
ジェームス・リジィ
THE BIG AND LITTLE AP...詳細
笹倉鉄平
白い時間詳細
ラッセン
ツー・ハーツ・アズ・...詳細